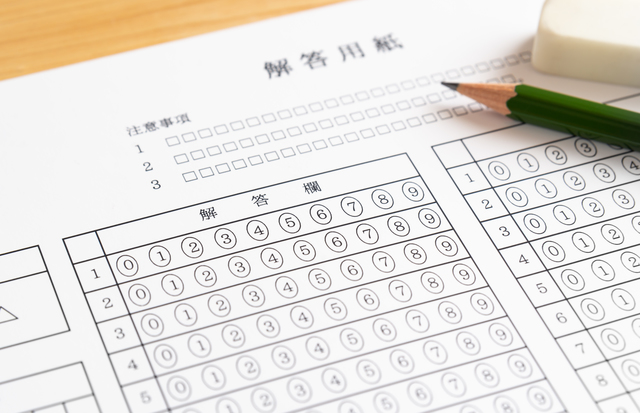目次
- クリーニング業法は、クリーニング師試験の得点源
- 第1条:目的
- 第2条:定義
- 第3条:営業者の衛生措置等
- 第3条の2:利用者に対する説明義務等
- 第4条:クリーニング師の設置
- 第5条:営業者の届出
- 第5条の2:クリーニング所の使用
- 第5条の3:地位の承継
- 第6条:クリーニング師の免許
- 第8条:登録
- 第8条の2、3:クリーニング師の研修・業務従事者に対する講習
- 第9条:業務従事者の業務停止
- 第10条:立入検査
- 第10条の2:措置命令
- 第11条:営業停止処分等
- 第12条:免許取消
- 衛生管理分野の出題傾向まとめ
- クリーニング師資格の取り方から活かし方まで、知っておきたい情報はこちら
- クリーニング師試験は、正しい理解で確実に合格できる
- この記事の提供:洗濯代行サービス「しろふわ便」について
クリーニング業法は、クリーニング師試験の得点源
クリーニング師試験の中でも、クリーニング業法に基づいて出題される「衛生法規に関する知識」は毎年必ず出題される重要科目です。
この分野では、クリーニング業法に基づく条文や行政上の手続き、衛生措置などが中心に出題されます。
内容自体は法律に基づく明確な決まりごとなので、きちんとクリーニング業法を理解すれば得点を取りやすい分野といえます。
本記事では、クリーニング業法の主要な条文構成をもとに、出題傾向と要点を整理します。
第1条:目的

クリーニング業法の目的は、クリーニング業の衛生水準を確保し、公衆衛生の向上を図ることにあります。
つまり単に衣類を洗うだけでなく、利用者の健康・衛生環境の維持が目的であることを理解しておきましょう。試験では条文の「公衆衛生の向上」「公共の福祉」「利用者の利益の擁護」などの表現が正誤問題として出題されます。
第2条:定義
ここでは「クリーニング業」「クリーニング所」「クリーニング師」などの基本用語が定義されています。
特に「クリーニング業」とは、他人の衣類等を預かって洗濯する営業を指すものであり、家庭内での洗濯や自家使用は含まれません。また「クリーニング師」は国家資格を有し、衛生管理を行う専門職として明記されています。試験では「営業者」の定義や種別について問う問題や、クリーニング所の定義に関する問題が多く出題されています。
第3条:営業者の衛生措置等
営業者は、クリーニング所において清潔な設備の維持・害虫防除・換気・作業員の衛生教育などを行う義務があります。
試験では、「設備の必要条件」「洗濯機・乾燥機・機材の取り扱い」「洗たく物の区分」「消毒について」など、クリーニング所の衛生措置に関する問題が多く出題されています。
第3条の2:利用者に対する説明義務等
営業者は、利用者に対して洗濯の方法や苦情の申し出先などを明示する義務を負います。
試験では、明示すべき内容と明示方法を問われることが多いようです。
第4条:クリーニング師の設置
クリーニング所には、必ず1名以上のクリーニング師を設置しなければなりません。
この条文は頻出項目です。出題では「常時」「1名以上」「営業者がクリーニング師である場合」など条文の表現を正確に覚えておく必要があります。
第5条:営業者の届出
クリーニング所を開設する場合は、都道府県知事への届出義務があります。
変更や廃止の際にも同様に届出が必要です。試験では届出の内容や時期、届出先などがよく問われています。
第5条の2:クリーニング所の使用
届出後に都道府県知事等の検査を受けたクリーニング所のみ、日本国内では営業可能となっています。
試験では、第5条の営業者の届出に関する設問と絡めて問われることが多いようです。
第5条の3:地位の承継
営業者が死亡した場合や法人の合併などで営業を承継する場合、一定期間内に届出を行えば営業を継続可能です。
試験では「死亡」「相続」「合併」など承継パターンの違いを問う問題が出ることがあります。
第6条:クリーニング師の免許
免許は都道府県知事が付与し、免許取得地以外の全国で有効となります。
免許はクリーニング師試験に合格した者に限り、合格した地の都道府県知事に申請することが出来ます。免許証の交付や再発行など、手続きの範囲も試験で出題されています。
第8条:登録
免許を受けたクリーニング師は、都道府県ごとの登録簿に記載されます。
また、登録内容に変更があった場合は速やかに届け出なければなりません。試験では、登録内容の変更があった場合の申請時期や内容について問われることが多いようです。
第8条の2、3:クリーニング師の研修・業務従事者に対する講習
クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、厚生労働省令により一定期間での研修を受けることが定められています。
また営業者は従業員に対し、規定の研修を受ける機会を与えることも同様に定められています。試験ではクリーニング師の研修受講や、営業者の講習についての問題が出題されています。
第9条:業務従事者の業務停止
業務従事者の就業が公衆衛生上不適当と認められる場合、都道府県知事は業務停止命令を出すことができます。
停止期間や違反内容に関する設問が出題されることもあります。
第10条:立入検査
都道府県知事から権限を委任された自治体職員は、必要に応じてクリーニング所の立入検査を行うことが出来ます。
検査権限は誰にあるか?」という形式で出題されやすい条項です。
第10条の2:措置命令
営業者が規定に違反していると認められた場合、行政は改善命令(措置命令)を出すことができます。
この命令に従わない場合、次に説明する「営業停止処分」や「免許取消」に発展します。
第11条:営業停止処分等
法令違反や措置命令への不服従などがあった場合、営業停止処分を受けることがあります。
期間は違反内容に応じて都道府県知事が決定します。この条文では、「業務停止」と「免許取消」の違いを正確に把握しておくことがポイントです。
第12条:免許取消
クリーニング師が業法違反、虚偽申請、または著しい不正行為を行った場合、免許が取り消されることがあります。
倫理規定に関する条文として出題されやすい部分です。
衛生管理分野の出題傾向まとめ

衛生法規に関する知識は、毎年全体の約20〜25%を占める出題領域です。
特に第1条から第8条(目的〜クリーニング師の登録や研修)は頻出で、基本用語や行政手続きを中心に出題されます。条文ごとに内容を理解し、暗記ではなく「なぜこの取り決め、措置が必要か」を意識すると得点に繋がります。
クリーニング師資格の取り方から活かし方まで、知っておきたい情報はこちら

クリーニング師資格の受験を考えている方や、取得後に活かしたい方へ。
試験の概要から学習法、開業までのステップをまとめた記事をこちらでご紹介します。
クリーニング師の受験資格と条件|誰でも挑戦できる国家資格を徹底解説
クリーニング師の受験ガイド|試験概要から合格までの流れを解説
洗濯代行とクリーニング師免許の活かし方|資格を強みに副業から独立を目指すフランチャイズモデル
クリーニング師試験は、正しい理解で確実に合格できる

衛生法規に関する知識は条文を読み解く必要があり一見難しそうに見えますが、出題は法律の条文に忠実な内容が中心です。
過去問を繰り返し学習すれば、短期間でも確実に点数を積み上げられる分野といえます。
クリーニング師試験全体も、地道に知識を積み重ねれば十分合格が可能です。
専門的な知識を身につけ、現場でも活かせるよう理解を深めていきましょう。
この記事の提供:洗濯代行サービス「しろふわ便」について

本記事は、東京都内で洗濯代行サービスを提供している「しろふわ便」が作成しました。
しろふわ便は、毎日の洗濯にかかる「洗う・乾かす・たたむ」の手間をまるごとおまかせできる、東京都内最大級の洗濯代行サービスです。ご自宅までの集配つきで、忙しい方や家事の負担を減らしたい方に多くご利用いただいています。
私たちのこだわりは、高品質な仕上がりと、時短の両立。時間に余裕ができるだけでなく、ふんわりと気持ちのよい仕上がりをお届けできるよう、丁寧な作業を心がけています。
暮らしの中の洗濯を、もっとラクに、もっと快適に。
しろふわ便について、詳しくは公式サイトをご覧ください。