目次
クリーニング師とは?国家資格としての位置づけ
クリーニング師は、クリーニング業法に基づいた公衆衛生・クリーニング業に関する専門的な知識と技術を持ち、クリーニング所の衛生管理を担う国家資格です。
クリーニング師はクリーニング業の実務だけでなく、店舗の衛生指導、設備管理なども行う専門職として位置づけられています。
この資格を持つことで、クリーニング所を開設・運営するための法的要件を満たすことができ、業界内では必須の免許とされています。
試験の概要と実施方法

クリーニング師試験は、日本国内の各都道府県において年1回実施されています。
国家資格ではありますが、実施・管理は自治体ごとに行われるのが特徴となっています。
多くの自治体では、学科試験と実技試験の2部構成となっており、両方の合格をもって免許申請が可能となります。
| 試験区分 | 内容 | 主な出題範囲 |
|---|---|---|
| 学科試験 | 筆記(マークシートまたは記述) | 衛生法規・公衆衛生・洗濯理論 |
| 実技試験 | 実作業の実演 | 繊維の鑑別・しみ抜き・アイロン操作・仕上げなど |
試験日程や受験手数料は、都道府県によって異なります。
例年、秋から冬にかけて(9〜2月頃)実施されることが多く、願書受付は1〜2ヶ月前に行われています。
自治体による違いと注意点
クリーニング師試験は全国一律の国家資格である一方で、出題傾向・試験方法・合格率は自治体によって差があります。
例えば東京都や大阪府など大都市圏では受験者数が多く過去問題などの情報も公開されている一方、地方では受験者が限られ、問題の傾向なども公開されていないことがあります。
また、実技試験は「アイロン仕上げ」「繊維の鑑別」「しみの鑑別」など、地域によって重点が異なる場合もあります。
そのため詳細な日程・内容については、受験を希望する各都道府県の公式サイトを確認する必要があります。
試験の難易度と合格率

試験の合格率は自治体によって異なりますが、例年60〜80%程度が目安とされています。
出題内容は洗濯の基礎知識から公衆衛生・衛生管理、クリーニング業法、洗剤の化学的性質まで幅広く、実務経験がない受験者にとってはやや難易度が高い試験です。
一方で、クリーニング業の実務に携わっている方は日常業務とリンクする内容が多く、比較的理解しやすい傾向にあるといえます。
どんな人が受験しているのか?
受験者の多くは、以下のような背景を持つ方々です。
- クリーニング店・リネンサプライ業など、現場経験者
- 新規で独立・開業を目指す個人事業主
- ホテルや病院など、施設内クリーニング部門の担当者
- 学生・主婦など、家庭での洗濯知識を専門資格に活かしたい人
男女問わず幅広い層が受験しており、特に近年では30〜50代の受験者が多く見られます。
また近年では洗濯代行やランドリーサービス業の拡大に伴い、新規の参入者が資格を取得してクリーニング所を設立するケースも増えているようです。
合格までに必要な勉強時間と内容
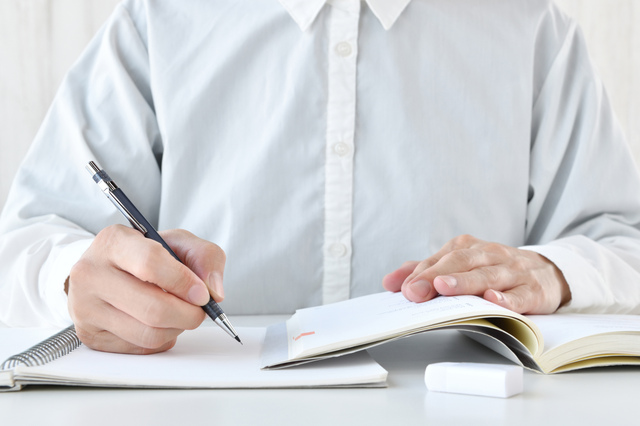
独学でも十分合格は可能ですが、出題範囲が広いため、体系的な学習が求められます。
一般的に、勉強期間は実技を含めて2〜3ヶ月程度、総学習時間は50〜100時間程度が目安といえるでしょう。
| 学習分野 | 主な内容 | 学習ポイント |
|---|---|---|
| 衛生法規 | クリーニング業法、公衆衛生法 | 条文の内容を正確に理解する |
| 洗濯理論 | 繊維・洗剤・温度条件 | 素材ごとの処理法、実務に関する知識を整理する |
| 公衆衛生 | 公衆衛生・感染症等の知識 | 衛生法規を学習 |
| 実技 | アイロン、しみ抜き、仕上げ技術 | 作業手順と技術を重点的に学習 |
テキストや過去問題集の活用に加え、クリーニング業組合などが主催する講習会を受講することで、実技試験への対策が効率的に行えます。
さらに詳しく知りたい方はこちら
クリーニング師試験の受験資格や免許取得後の活かし方について、別記事で詳しく解説しています。
クリーニング師の受験資格と条件|誰でも挑戦できる国家資格を徹底解説
洗濯代行サービスの開業に必要な資格とは?クリーニング師取得と流れ・注意点を解説
よくある質問|クリーニング師試験に関するQ&A

ここでは、受験を検討している方からよく寄せられる質問をまとめました。初めて受験を考えている方でも、試験の流れや準備のイメージを掴んでいただけます。
Q1. 受験資格に年齢や学歴の制限はありますか?
A. 特別な制限はありません。中学卒業以上の方であれば誰でも受験可能です。
学歴・職歴は問われませんが、実技試験の内容には一定の作業スキルが求められるため、早めの準備が重要です。
Q2. 試験対策は独学でも大丈夫ですか?
A. 独学でも十分合格可能です。
ただし、出題範囲が広く、専門用語や衛生法規など初学者には馴染みのない分野も含まれます。市販のテキストと過去問題集を併用し、自治体や業界団体が実施する講習会を受けるのがおすすめです。
Q3. 実技試験はどんな内容ですか?
A. 実技試験では、アイロン仕上げ・しみ抜き・繊維の鑑別などの基本作業が課されます。
試験官が作業手順や仕上がりをチェックするため、手際の良さや清潔な操作が評価ポイントになります。実務経験がなくても、事前に練習すれば対応可能です。
Q4. 合格後はどのように資格を活かせますか?
A. 合格後、自治体に免許申請を行うことで「クリーニング師」として登録されます。
この資格があれば、クリーニング所を開設・運営できる法的要件を満たすことになります。近年ではクリーニング店勤務だけでなく、洗濯代行サービスやリネン業、ホテル業界などでも活躍の場が広がっています。
Q5. 洗濯代行サービスを始めたい場合、この資格は必要ですか?
A. はい。
洗濯代行サービスも「クリーニング所」として扱われるため、開業にはクリーニング師の免許が必要です。特に独立開業を目指す場合は、資格取得が第一歩となります。
Q6. 資格を取った後に独立するのは難しいですか?
A. 一般的に個人での開業は初期費用やノウハウの面でハードルがあります。
しかし、洗濯代行しろふわ便のようなフランチャイズ制度を利用すれば、資格取得から開業・運営まで一貫したサポートを受けられます。資格を活かして安定した収益を得たい方には特におすすめです。
「クリーニング師」資格取得はクリーニング業界への第一歩

クリーニング師は、クリーニング業のみならず衛生管理の専門家として信頼される資格です。
試験は自治体ごとの実施ではありますが、正しい学習計画を立てれば決して難関ではありません。
クリーニング業に従事されている方、洗濯技術を学んでビジネスに役立てたい方は、受験を通じて知識を広げる良い機会となるでしょう。
この記事の提供:洗濯代行サービス「しろふわ便」について

本記事は、東京都内で洗濯代行サービスを提供している「しろふわ便」が作成しました。
しろふわ便は、毎日の洗濯にかかる「洗う・乾かす・たたむ」の手間をまるごとおまかせできる、東京都内最大級の洗濯代行サービスです。ご自宅までの集配つきで、忙しい方や家事の負担を減らしたい方に多くご利用いただいています。
私たちのこだわりは、高品質な仕上がりと、時短の両立。時間に余裕ができるだけでなく、ふんわりと気持ちのよい仕上がりをお届けできるよう、丁寧な作業を心がけています。
暮らしの中の洗濯を、もっとラクに、もっと快適に。
しろふわ便について、詳しくは公式サイトをご覧ください。
しろふわ便の詳細はこちら

